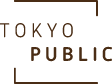社会福祉・医療現場のためのパワーハラスメント対策(第1回)「パワハラにならない「指導」とパワハラの境界線は?」
2025年07月07日
弁護士 白鳥秀明
社会福祉法人や医療法人の皆さまにとって、人材の確保・定着は最重要課題の一つです。スタッフが安心して能力を発揮できる職場環境を守ることは、良質なサービス提供の基盤となります。
今回は、パワーハラスメントをテーマに、管理者の皆さまが知っておくべき法的な知識を分かりやすく解説していきます。まずは、すべてのハラスメントの基本となる「パワーハラスメント(パワハラ)」を取り上げます。「これってパワハラ?」「どこからが指導で、どこからがパワハラなの?」といった疑問を解消していきましょう。
パワハラ相談は、年々増加しています
「パワハラ」という言葉が社会に浸透し、労働者の権利意識が高まるにつれて、全国の労働局に寄せられるパワハラの相談件数は、この10年で2倍以上に増加し、いじめ・嫌がらせに関する相談は数ある労働相談の中でトップの割合を占め続けています。
このような状況を受け、2019年には法律(労働施策総合推進法)が改正され、初めてパワハラの定義が定められました。そして現在、すべての事業者には、パワハラを防止するための措置を講じることが義務付けられています。
つまり、パワハラ対策は「努力目標」ではなく、法律で定められた「義務」なのです。
パワハラとは?代表的な「6つの類型」
では、どのような行為がパワハラに当たりうるのでしょうか。厚生労働省は、代表的な言動を以下の6つの類型に分類しています。ご自身の職場でのコミュニケーションを振り返りながら、確認してみてください。
1 身体的な攻撃
殴る・蹴るといった暴力行為はもちろん、相手に物を投げつけたり、カルテや机を叩いて威嚇したりする行為も含まれます。
2 精神的な攻撃
人格を否定するような発言、他の職員が大勢いる前での厳しい叱責(公開叱責)、必要以上に長時間・繰り返し叱責する行為などです。業務上の注意であったとしても、その伝え方や場所、頻度が不適切であれば、精神的な攻撃と判断される可能性があります。
3 人間関係からの切り離し
特定の職員を意図的に無視したり、会議や業務に必要な連絡事項を伝えない、一人だけ別の部屋に席を移すといった行為が該当します。
4 過大な要求
明らかに遂行不可能な業務目標を課したり、新人看護師に必要な指導を行わないまま、ベテランでなければ対応できないような業務を命じたりする行為です。
5 過小な要求
本人の能力や経験とはかけ離れた、誰にでもできるような簡単な作業ばかりを命じたり、あるいは全く仕事を与えなかったりする行為です。例えば、管理職としての経験が豊富な職員に対し、合理的な理由なく、一日中シュレッダー作業だけをさせるようなケースが考えられます。
6 個の侵害(プライベートへの過度な介入)
交際相手や家族に関すること、性的指向・性自認(SOGI)など、業務とは無関係な私的な情報をしつこく聞いたり、本人の許可なく他の職員に言いふらしたり(アウティング)する行為です。これらの6つはあくまで代表例です。これらに当てはまらなくても、パワハラと判断されるケースはあります。法律上の「パワハラ」と判断される3つの要件上記の6類型のような行為があったとしても、それだけで直ちに法律上のパワハラとなるわけではありません。法律(パワハラ防止法)上の「職場におけるパワーハラスメント」は、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
要件① 「優越的な関係」を背景とした言動であること
「優越的な関係」とは、単に職務上の地位(役職)が上であることだけを指すわけではありません。
もちろん、部長から課長へ、師長から一般の看護師へ、といった関係は分かりやすい例です。しかし、同僚や部下であっても、以下のような場合は「優越的な関係」に立ち得ます。
・その職員の協力がなければ、業務が円滑に進められない場合
・専門知識や経験が豊富で、その職員に逆らいにくい関係がある場合
・集団で一人の上司の指示を無視し、業務を妨害する場合(部下から上司へのパワハラ)
医療・福祉の現場はチームワークが不可欠です。そのため、同僚間であっても「優越的な関係」は生まれやすいと言えるでしょう。
要件② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
これが、「適正な指導」との最も重要な境界線です。
業務上のミスや改善すべき点について、必要な指示や指導を行うこと自体は、もちろんパワハラではありません。
しかし、その言動が「社会通念に照らして」、業務上の必要性がない、または、必要性があったとしてもやり方・手段が不適切で許容範囲を超えている、と判断されると、この要件を満たすことになります。
判断にあたっては、「指導の目的」「労働者の問題行動の程度」「言動の態様や頻度」などが総合的に考慮されます。
要件③ 労働者の就業環境が害されること
その言動によって、労働者が身体的または精神的に苦痛を感じ、職場で能力を発揮するのに重大な支障が生じる状態を指します。
この判断は、言われた本人がどう感じたかという主観だけでなく、「同じような状況で、同じ言動を受けたら、社会一般の平均的な労働者であれば、就業環境が害されると感じるかどうか」という客観的な基準で判断されます。
まとめ:今回のポイント
今回は、パワハラの定義について解説しました。
・パワハラには代表的な6つの行為類型があること。
・法律上のパワハラは、「①優越的な関係」「②業務の適正な範囲を超える」「③就業環境を害する」という3つの要件で判断されること。
「指導のつもりが、パワハラと受け取られてしまった」という事態を避けるためにも、まずはこの定義と判断基準を正しく理解することが、すべての対策の第一歩となります。
今後、パワハラを防止するために、法律が事業者にどのような義務を課しているのか、そして、万が一パワハラが発生してしまった場合に誰がどのような責任を負うのかについて解説していきます。