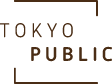カテゴリー
社会福祉・医療現場のためのパワーハラスメント対策(第2回)「職場でパワハラ発生!法人が問われる責任と10の防止策」
2025年08月27日弁護士 白鳥秀明
もしパワハラが起きたら?問われる2つの法的責任
1 行為者(加害者)個人の責任
2 使用者(法人・事業者)の責任
使用者責任(民法第715条)
職員を雇用して事業の利益を上げている以上、その職員が「業務に関連して」他者に与えた損害についても、法人が責任を負うべき、という考え方です。
安全配慮義務違反(労働契約法第5条)
法人は、職員が心身の安全を確保しながら働けるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。職場でパワハラが起こるのを防げなかったり、発生後も放置したりすることは、この義務に違反する「債務不履行」にあたります。
責任を問われないために。法律が求める「10の防止措置」
【CATEGORY 1】 方針の明確化と周知・啓発
1 パワハラの内容と禁止方針の明確化・周知
2 行為者への厳正な対処方針の規定化・周知
就業規則などに「パワハラを行った者は懲戒処分の対象となる」と明確に規定し、その内容を全職員に周知します。
【CATEGORY 2】 相談体制の整備
1 相談窓口の設置と周知
職員が安心して相談できる窓口を設置します(人事課、信頼できる職員、外部委託機関など)。誰が担当者で、どう連絡すればよいかを明確に周知することが重要です。
2 相談への適切な対応準備
相談担当者が、プライバシーを守りつつ、公平・迅速に対応できるよう、対応マニュアルの整備や研修を行います。
【CATEGORY 3】事後の迅速・適切な対応
1 迅速かつ正確な事実関係の把握
相談があった場合、相談者と行為者とされる双方から聴取し、事実関係を迅速に確認します。主張が食い違う場合は、第三者からも話を聞くなど、客観的な調査を行います。
2 被害者への配慮措置
パワハラの事実が確認できたら、速やかに被害者をケアします。行為者との配置転換、謝罪の場の設定、メンタルヘルス不調への対応など、状況に応じた措置を講じます。
3 行為者への措置
事実に基づき、就業規則に則って行為者への懲戒処分などを検討・実施します。配置転換や再発防止研修なども有効です。
4 再発防止措置
改めて全職員にパワハラ禁止の方針を周知したり、研修を実施したりするなど、二度と同様の問題が起きないための対策を講じます。
【CATEGORY 4】上記と併せて講ずべき措置
1 相談者等のプライバシー保護
相談したことや、事実確認に協力したことなどを理由に、不利益な取扱い(解雇、降格、異動など)をされない旨を規定し、周知します。
2 不利益取扱いの禁止
改めて全職員にパワハラ禁止の方針を周知したり、研修を実施したりするなど、二度と同様の問題が起きないための対策を講じます。
まとめ:今回のポイント
-
- パワハラが発生すると、行為者本人だけでなく、使用者である法人も損害賠償責任を問われる可能性がある。
- 法人の責任は、「必要な対策を怠った」場合に発生する。
- 法律が定める「10の防止措置」を普段から講じておくことが、職員と職場を守り、法人の責任を果たす上で不可欠である。
より具体的な対策については、厚生労働省のウェブサイト「あかるい職場応援団」も参考になります。
次回は、これまでの裁判でどのような言動がパワハラと判断されたのか、具体的な事例を基に、より実践的な視点から解説していきます。
タグ: パワハラ, 医療現場, 社会福祉, パワーハラスメント対策, 法律